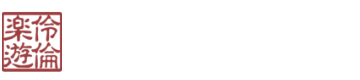ニュース
-
2025.05.10
演奏会
no.43聴きどころ⑤ 三臺塩 序破急
管絃「三臺塩 序破急」芝祐靖復曲構成(1998年)
「三臺塩(三台塩)」は、唐の則天武后が、張文成という男を思慕し、その情を写したこの曲を作った、と伝えられています。
もとは序破急が揃っており、今も「急」の部分は平調の曲として演奏されていますが、序と破は伝えられていません。
「破」は古譜が残っていますが、「序」は犬上是成が舞師であった時、この序を秘して伝えなかったので、平安期にすでに伝承が途絶えてしまったといいます。
芝祐靖師は、この曲を序破急揃った一具として演奏するため、今に残る「三臺塩急」の特徴ある旋律を用いつつ「序」を作り、「破」は古譜から復曲した旋律に「急」独特の旋律も組み込んで、延只八拍子の楽曲に編み出しました。
延只八拍子は今ではほとんど演奏されることのない拍子です。
「三臺塩」の「塩」は「艶」にも通じるといいます。則天武后の艶やかなエピソードを持つこの曲をゆったりとお楽しみください。
-
2025.05.03
演奏会
no.43聴きどころ④ 祈響第十二番
〇横笛二重奏 祈響第十二番 芝祐靖作曲 (1990年)
「祁響」は龍笛奏者のための練習曲として芝祐靖が作曲したもので、この十二番のみが二重奏曲で、他は独奏曲となります。芝作品として人気の高い龍笛独奏曲「一行の賦」や「白瑠璃の碗」も祈響シリーズの中の曲です。
龍笛奏者が、現代曲の要求に応じられる技法と表現力を持つ訓練をするための練習曲として作曲されたというだけあって、高度な技巧が要求される曲ですが、同時に豊かな音楽性も感じられます。
「祁響」とは、楽しい演奏と、良い響きが広がってほしいという作曲者の願いが込められた曲名だといいます。
5月21日に久しぶりに再演され、ホールに広がるこの曲の響きをどうぞお楽しみください。
-
2025.04.30
演奏会
no.43聴きどころ③ 風香調調子・急胡相問
〇正倉院復元楽器合奏 「風香調調子」芝祐靖作曲(1986年)、
「急胡相問」芝祐靖復曲(1987年)敦煌の千仏洞第十七窟で経典や文書と共に発見された琵琶譜は、唐代に書かれたと思われるもので、当初は解読不能といわれていましたが、日本の雅楽の伝承が手がかりとなって解読が可能となりました。芝祐靖はこの琵琶譜に記された音と音との間に存在した「古代の旋律」を見出すことは不可能でも、各楽器の特性や音律を考えあわせれば、かなりのところまで近づけるのではないかと考えて旋律を探り、25曲を正倉院復元楽器を用いた合奏へとオーケストレーションしました。
今回演奏する「急胡相問」は、曲名から西域の胡の国の相問歌(相聞歌=恋の歌)の急(序破急の急)と解釈して、軽快な合奏部分のなかに歌垣(恋の二重唱)を思わせる対話的な部分が配された曲です。
また、「風香調調子」は敦煌琵琶譜に記された曲ではありませんが、唐楽では楽曲の前に調子を演奏することに倣い、芝祐靖が付した曲になります。会場を「風香調」の雰囲気に満たす各楽器の音色をお楽しみください。
-
2025.04.21
演奏会
no.43聴きどころ② 遊児女
〇新撰楽譜より 遊児女(芝祐靖復曲 1994年)
「遊児女」は盤渉調に属する遠楽(現在は伝承されていない雅楽曲)です。
今回は、伶楽舎の第一回目となる雅楽演奏会(1994年6月16日、東京文化会館小ホール)のために、芝祐靖が訳譜した曲を演奏します。この時演奏された「曹娘褌脱」の前に奏する道楽(入場音楽)として訳譜されたもので、通常のような管絃の編成にはせず、正倉院復元楽器である「排簫」で奏するフリーリズムの曲に訳されています。
芝はこの曲について、
「古代中国、隋の煬帝の作とつたえられる『遊児女』ですが、訳譜から浮かび上がった音楽は、別称の「恋女子」の曲名の方が合っているかもしれません。」
と書いています。どのような音楽でしょうか。お楽しみに。
-
2025.04.21
演奏会
no.43聴きどころ① 青葉の舞
神前神楽 青葉の舞(芝祐靖作曲 宮田まゆみ作舞 2007年)
仙台にある大崎八幡宮の御鎮座400年記念して芝祐靖が作曲、宮田まゆみが作舞した曲で、2008年に初演されて以来、大崎八幡宮の外で上演されるのは今回が初めてとなります。
曲は音取、破、道行乱声、急、退出音声からなり、「破」の神楽歌は男声的に力強く、「急」の神楽歌は軽快に宴のさまをイメージしたもの、その間には行軍をあらわす雅楽合奏「道行乱声」を配するという変化に富んだ曲調となっています。
神楽歌には、初代千代藩主である伊達政宗公が仙台の末長い繁栄を願って詠んだ和歌
「入りそめて 国ゆたかなる みぎりとや 千代(ちよ)とかぎらじ せんだいのまつ」
が歌われます。
舞は4人の女性によるもので、今回は大崎八幡宮の巫女さんと伶楽舎員が共に舞う予定です。
社殿彫刻の鶴が刺繍された「狛鉾」の装束と同系の美しい装束に天冠をつけ、手には真榊や花束を持って舞う舞姿にどうぞご注目ください。
-
2025.03.03
お知らせ
ラジオ放送のお知らせ
遠藤徹先生がお話をされている「カルチャーラジオ 芸術その魅力雅楽入門〜日本最古の伝統音楽〜」(NHKラジオ第2)で、伶楽舎音楽監督・宮田まゆみ、および伶楽舎の演奏が取り上げられます。3/5の放送では伶楽舎音楽監督の宮田まゆみも復曲に関わった太食調入調に関するお話と演奏、3/12の最終回では伶楽舎の演奏する「皇帝三台」も放送されます。・3/5(水) 20:30〜21:00「秘曲の物語 太食調入調」・3/12(水) 20:30〜21:00「正倉院の楽器 皇帝三台」※ 番組最後で、伶楽舎の演奏による「皇帝三台」を聴くことができます。※ いずれも再放送は翌週水曜日の10:00〜10:30。※ NHKのらじる★らじるでも1週間配信されます。演奏鑑賞は番組の最後10分程度のようです。よろしければどうぞお聞きになってみてください。 -
2025.01.17
演奏会
第十七回雅楽演奏会聴きどころ ③輪廻 division11 (猿谷紀郎作曲 委嘱初演)
猿谷紀郎さんは、1997年に一柳慧氏の委嘱によりTIME(Tokyo International Music Ensemble)公演のために、邦楽器と雅楽器のために「臨照(りんしょう)」を作曲されていますが、その後も伶楽舎の委嘱により「凜刻(りんこく)」「綸綬(りんじゅ)」を作曲いただくなど、雅楽器を用いた曲をいくつも作曲されています。
今回は管絃2管通りの11人編成にて、新曲を書いていただきました。
Division 11 とは、文字通りこの曲が11の部分からなることを意味しますが、11には他にも隠されたいろいろな意味があるようです。
「雅楽の響きの中に、未来永劫続く、輪廻の夢を見ていただければ幸いです」とのメッセージをいただいております。
どうぞご期待ください。 -
2025.01.07
未分類
新年のご挨拶
新年あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
今年、伶楽舎は創立40周年の年を迎えます。
40周年記念、第一弾として以下の自主公演を予定しています。
1月24日(金)19:00伶楽舎第17回雅楽演奏会@紀尾井ホール
https://reigakusha.com/home/concert/4921長年取り組んできた現代雅楽の傑作、武満徹作曲「秋庭歌一具」、伶楽舎創立者の芝祐靖先生の代表作、唯一無二の心踊る管絃曲「舞風神」、そして40周年記念として、ずっとお世話になっている猿谷紀郎さんの「輪廻 Division 11」(委嘱初演)を演奏いたします。
一同、気持ちも新たに精進して臨みたいと存じます。
【以降の自主公演予定】
5月21日(水) 雅楽コンサートno.43 古典様式の作品を集めて〜伶楽舎40周年記念(芝祐靖作品演奏会その5)〜(仮題)@渋谷・さくらホール
-
2024.12.28
放送・放映
NHK Eテレ 芸能きわみ堂で笙の魅力を紹介
NHK Eテレ 芸能きわみ堂 「大久保さん、笙の世界に遊ぶ」12月27日(金) 午後9:00〜午後9:30で伶楽舎音楽監督 宮田まゆみが出演し、お話や演奏を通じて笙の魅力を紹介しました。
笙工房で笙が制作されていく興味深い映像もあり、伶楽舎による管絃合奏も少し挿入されております。放送後NHKプラスで1週間配信されますので、見逃された方はこちらをどうぞ。 -
2024.12.17
演奏会
第十七回雅楽演奏会 聴きどころ②舞風神 序破急(芝祐靖作曲)
管絃のための「舞風神」序・破・急(2008年作曲)は、ミュージック・フロム・ジャパン創立35周年を祝って作曲された曲で、2010年2月北米ツアーの折、ニューヨーク・マーキンコンサートホール公演で初演されました。
京都・蓮華王院(三十三間堂)にある風神像が、風袋を絞りつつ鳴き叫び、今にも飛びかかろうとしている姿に迫真の気勢を感じ、この風神像のイメージで作曲されたとプログラムノートにあり、委嘱者のMusic from Japanの頭文字MFJを生かして「舞風神」という曲名がついたと聞いています。
この曲は、雅楽の古典形式に倣って、序・破・急の三章となっています。
「序」は、静謐の蓮華王院の佇まいを表し、フリーリズムの序の様式。
ゆったりした「破」の部分は、平安時代から三十三間堂に安置され、世の安穏を祈り続けている穏やかな仏像群を表しています。
「急」は、想像の中で、風神像が雲座から飛びおりて軽やかに舞い回る姿が、軽快なリズムと旋律で表現されています。
譜面に「跳拍子」と記されている通り、跳ねるように楽しい曲で、作曲者の豊かな遊び心を感じる名曲です。